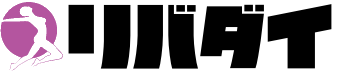はじめに|女性の“痩せにくさ”には理由がある
「同じ運動をしているのに、生理前になると太る」「ダイエットが続かないのは意思が弱いから?」――実はその正体は“ホルモンのリズム”にあります。2025年現在、フェムテックアプリを活用することでホルモン変動を味方に付けた「周期連動型ダイエット」が現実になりつつあります。本記事ではその仕組みと実践法を、体験談とQ&A形式で解説します。
Q&A|ホルモンリズムを活用するには?
Q1:ホルモンリズムって何?
A:女性の体は月経周期に応じて、エストロゲンやプロゲステロンといったホルモンが日々変化しています。これにより代謝、食欲、むくみ、気分なども影響を受けます。周期は主に4つのフェーズに分かれます。
- ①月経期(リセット期)
- ②卵胞期(痩せやすい期)
- ③排卵期(不安定期)
- ④黄体期(太りやすい期)
Q2:それぞれの時期に何をすればいいの?
A:以下が基本方針になります:
- 月経期: 体を休め、温める。栄養は鉄・亜鉛・ビタミンC重視。
- 卵胞期: 運動・食事制限を最も活発に。有酸素+筋トレが効果的。
- 排卵期: 情緒不安定に注意。食事バランスを意識し、睡眠を確保。
- 黄体期: むくみやすいので塩分控えめ。腸活やリラックスが鍵。
Q3:どうやって自分の周期を把握するの?
A:フェムテックアプリ(例:ルナルナ、Flo、Clueなど)を使えば、自動的に周期を記録・予測できます。さらに最近のアプリは「その日のホルモン状態に基づくアドバイス」も提供してくれるため、日々の行動指針に役立ちます。
体験談|「太りやすい時期」に逆らわないダイエット
背景
筆者(30代・女性・デスクワーカー)は、以前まで「毎日同じ運動・食事」をしていたが、結果が出ずに挫折を繰り返していた。フェムテックアプリ「Clue」を使い、3週間の周期連動型ダイエットを実施。
1週目|卵胞期:運動集中&糖質調整
代謝が最も上がる卵胞期に合わせて、朝のウォーキング+夜のHIITを導入。ご飯を雑穀米にし、たんぱく質量を1.5倍に設定。体重が1.4kg減。
2週目|排卵期〜黄体期:ゆる運動&腸活中心
排卵日前後はイライラが出やすく、ヨガや深呼吸を実施。黄体期は塩分とカフェインを抑え、味噌汁+発酵食品中心の食事に切替。体重は微減だが、むくみが大幅に軽減。
3週目|月経期:休息重視と内臓温活
散歩程度の運動と、温かい食事(スープ、しょうが入り雑炊など)で内臓温度を意識。周期の流れを意識しただけで「無理がないのに整う」感覚を実感。3週間で合計2.3kg減。
アプリ活用の具体例
- ● Clue:ホルモン状態を可視化+おすすめ行動提案
- ● FEMTIPS:体調、食欲、感情のリズム記録と提案
- ● ルナルナ:生理予測+ダイエットアドバイス連携
実践ステップ
- ステップ1: アプリを導入し、1〜2ヶ月分のデータを記録
- ステップ2: 各フェーズごとに運動・食事の基本方針をメモ
- ステップ3: 「今はどの時期か?」を毎朝チェックし、柔軟に行動
注意点とアドバイス
- ● ホルモンの状態には個人差があるため「自分の傾向」を知ることが大事
- ● PMSや月経痛が強い人は無理せず、婦人科の相談も視野に
- ● 生理周期が不安定な人は、まずリズムの可視化から始めよう
まとめ|「休む」こともダイエットのうち
ホルモンリズムを理解することで、「やる気が出ない」「食欲が止まらない」時期にも罪悪感を持たずに対応できるようになります。自分の体と向き合うことが最大の近道。フェムテックアプリと共に、あなたのリズムで続けられるダイエットを見つけてください。